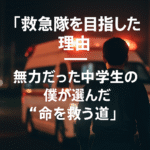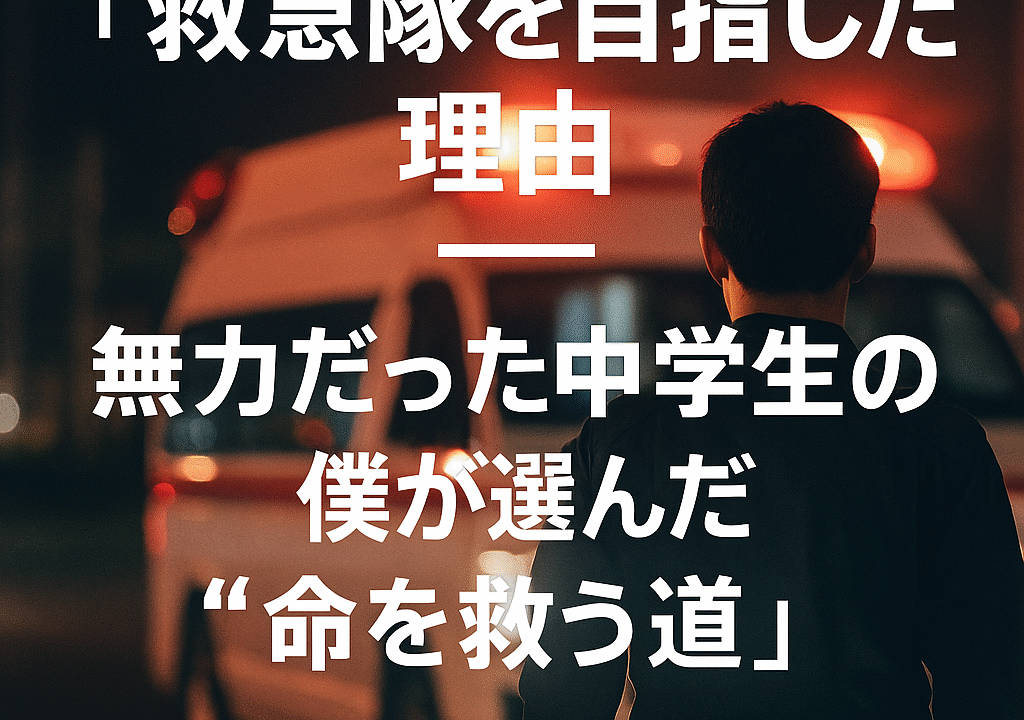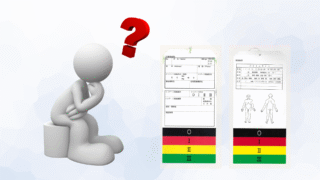目次
救命士という“希望”を知った、中学生の僕

中学生の頃、祖父が突然目の前で倒れた。
突然のことで呼び掛けることもできず、何もできずに立ち尽くすしかなかった。
手は震え、胸は苦しく、頭は真っ白――。
2階にいた父が異変に気づき、救急車を呼んだ。
幸い、一命はとりとめた。
そのとき感じた不安、後悔、悔しさが入り混じった複雑な感情。
二度と、あの気持ちを味わいたくない。
その後、「救急救命士」という資格があることを知った。
当時はまだあまり知られていなかったが、この資格を持てば人の命を救える。
“誰かの不安を取り除ける存在になれる”と思った。
だから私は、迷わず救命士の専門学校への進学を決めた。
念願の消防士に。でも現場では“ポンコツ”だった
学校を卒業し、夢だった消防の世界へ。
救命士として現場に立てる日が来た。
でも、現実は甘くなかった。
現場では緊張で体が動かず、何をしていいのか分からない。
報告もできず、事務処理もまったくできなかった。
先輩の洗濯物を畳んだり、食事の準備をするのが「自分の仕事」になっていた。
「こんなことをするために消防士になったんじゃない…」
そう思いながらも、変わりたいという思いだけは強かった。
要領は悪かった。でも、本気だった

私にできることは、人の何倍も時間をかけることだった。
- 若手勉強会を開いた
- 仮眠時間を削って勉強した
- 地水理(地理・水利)を車でまわって確認した
- 出動明けに眠い目をこすって事務処理をこなした
「自分にできることは何か?」
「何を身につければ、この現場で通用するのか?」
そんな問いを毎日のように自分に投げかけていた。
時間は削ってでも前に進もうとしていた。
いま思えば、本当に要領は悪かったと思う。
でも、その不器用さの中にあった“本気”は、今でも胸を張って言える。
命を救いたい。その思いが、すべての原点だった
誰かを救うためにこの道に進んだ。
なにもできなかったあの時の自分を、乗り越えるために、救命士になった。
現場で動けなくて悔しかった日も、
落ち込んで泣いた夜も、
「私じゃなくて先輩なら助かったかもしれない」と考えた日も、
全部、“誰かの命をつなぎたい”という思いが支えてくれた。
次回予告:ついに壊れた――気づいたのは、妻だった
どれだけ強くても、どれだけ覚悟があっても、心と体が限界を超えると、人は静かに壊れていく。
そして、それに気づいたのは自分ではなかった。
ある朝、出勤前に、妻がふとつぶやいた。
「なんで泣いてるの?」
次回、第2話では「限界に気づいた朝」と「救われる側になった瞬間」を描きます。
このブログを読んでほしい人へ
このブログシリーズでは、「働き方」「家族との向き合い方」「救急現場のリアル」を正直に綴っています。
- 救命士を目指す若者
- 救急隊で働く現役の方
- 仕事と家庭の狭間で悩んでいるすべての人
わたしの経験が、“誰かのヒント”になればうれしいです。